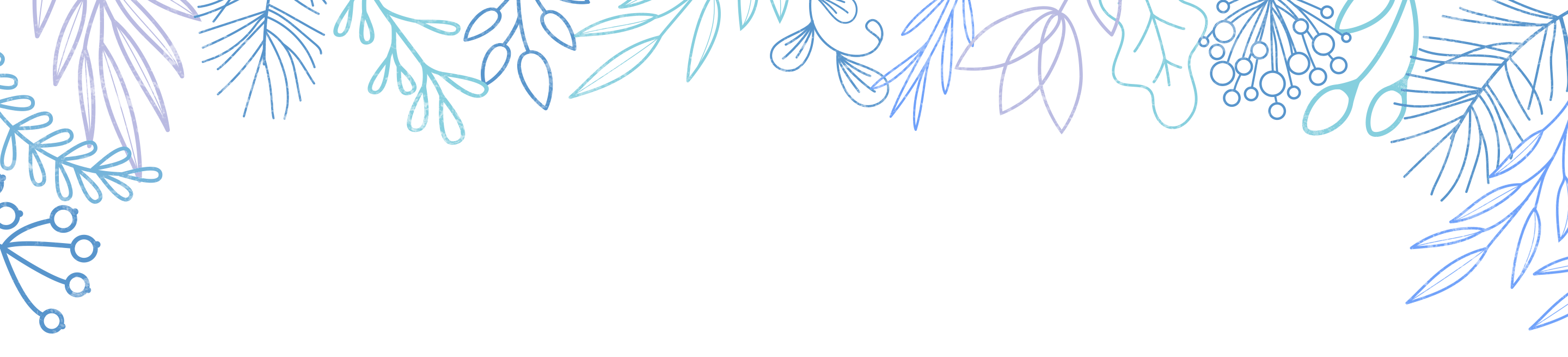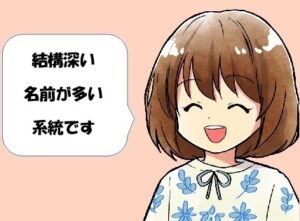
手軽に書けて、手軽に読める(と思われる)お薬の名前の由来シリーズ。
今日は糖尿病治療薬の中からSGLT-2阻害薬を取り上げました。
最近腎臓病や心不全にも適応拡大していて、面白いお薬たちですね。
今日は彼らの名前の由来に迫ってみましょう!
Contents
SGLT-2阻害薬の概要
名前の由来について見ていく前に、この系統のお薬について軽く復習しましょう。
「尿の生成の仕組み」と「糖の再吸収」
人間は腎臓で不要な老廃物を排出しますが、その第一段階として糸球体でろ過が行われます。
ここではコーヒーを淹れるときのフィルタと同じような原理で血液から老廃物を濾し出すのです。
フィルタを通らないたんぱく質や赤血球は濾し出されることはありませんが、小さな物質はその有用性のいかんを問わず、濾し出されてしまいます。
この段階の尿を原尿といいますが、この原尿は次の尿細管で99%再吸収され体内に戻ります。
この再吸収の段階で、アミノ酸や糖、ナトリウム、カリウム、リン等の重要な物質を回収します。
つまり、あたりかまわず濾し出して、大事なものは後から回収する!というのが人間の排出の機構なわけです。なかなか豪快かつ綿密な仕組みです。
しかし、ここで回収しきれない糖は尿となって出てしまいます。つまり血糖が高すぎると尿に糖が混じる糖尿病となるわけです。
SGLT-2阻害薬の作用機序
糖は一度原尿に濾し出された後に尿細管で再吸収されますが、ここで再吸収しないで外に出しちゃえ!というのが、SGLT-2阻害薬の簡単な作用機序です。
糖尿病というと尿に糖が出ることが悪いことのように聞こえますが、糖尿病の悪いところはその合併症であり、尿に糖が出ること自体はクリティカルな問題ではないのです。
SGLT-2阻害薬の利点と欠点
この作用機序には利点も欠点もあります。次の項目でまとめてみました。
利点としては、
血糖を直接下げるわけではないので、腎臓への負担が少なく、低血糖のリスクも低いです。
また血圧低下や体重の減少効果等もあります。
この辺の利点が心不全や腎臓病の適応拡大に寄与しているのですね。
欠点としては、
尿の糖分が増すため、尿路感染症等のリスク(特に女性)が上昇します。
また尿量が増えますので、脱水のリスク(特に高齢者)も上昇します。
余談ですが、通常、糖尿病の臨床試験では尿糖の確認項目がありますが、これらの試験ではありませんでした。
そうです、尿に糖を排出するこの薬で尿糖のチェックをしたら、一発で実薬だとばれてしまうからですね。
尿が泡立つから、患者さんでも分かっちゃうらしいです。
盲検崩壊。セルフキーオープンはまずいですよねー。
ちなみにこの部分、覚えておいてください。
これも余談ですが、SGLT-2阻害薬は実は特許取った順番通りの上市ではないのです。
途中で特許内容を利用して後から開発スタートした薬剤のほうが、先に上市したのです。
この辺の特許戦略の重要性は別記事で真面目に取り扱っていますので、今日は流しておきます。

フォシーガ
では、お薬の名前の由来に迫っていきましょう!
まずはアストラゼネカのフォシーガです。
一般名はダパグリフロジンとなります。
フォシーガは世界で初めて発売されたSGLT-2阻害剤で、100ヵ国以上で承認されています。
ついこないだ慢性腎臓病の適応追加を申請しましたね。
そんなフォシーガの名前の由来は、
患者のため、患者家族のため、医師のためをあらわす「for」と、
inhibit glucose absorption(糖の吸収を阻害する)の頭文字「iga」を
掛け合わせる(x)ことで、
他の血糖降下薬にはない新たな作用であることを表現している。
For-x-igaでフォシーガですね。
結構複雑なお名前してますね。
まさか作用機序を組み込んでいるとは思いませんでした。
そして「シ」は「xi」だったのか。
私はずっと蛇のイメージで、なんでだろうと悩んでいたのですが、
つい先日、風来のシレン5のリメイクが発売されたことで理由が判明しました。
こういうめちゃくちゃなイメージでもちゃんと覚えておけるならいいですよね。ね?
ジャディアンス
次はベーリンガーインゲルハイムのジャディアンスです。
一般名をエンパグリフロジンと言います。
エンパグリフロジンはリアルワールドデータを用いた研究(Empagliflozin comparative effectiveness and safety (EMPRISE))で、DPP-4阻害薬との比較をしていたのが面白かったですね。
さて名前の由来ですが、
Ja(ポジティブ,ドイツ語の”Yes”)と Radiance(輝き)から
2型糖尿病の患者さんに未来へのポジティブな輝きを与える薬剤という意味。
ド、ドイツ語。
そうだ、ベーリンガーはドイツの会社でした。
未来へのポジティブな輝きを与えるっ!!
なんてかっこいいんでしょ。
それにドイツ語ってところがまた洒落てますね(偏見)
私はシャンプーのイメージでした。
アジエンスというシャンプーのせいですね。
似てません?
ちなみにアジエンスは“Asian”“Essence”“Science”に由来するらしいので、かすってもいませんね。
いやシャンプーみたいな名前だし、尿に糖を出すということで、
すみません。
覚え方が酷いですね。
しかし忘れることはありません。
誰にも言うことはありません。
ここだけの話にしておいてください。
スーグラ
次はアステラスのスーグラを見てみましょう。
一般名はイプラグリフロジンですね。
スーグラは一番初めに1型糖尿病で適応追加とったSGLT-2だったと思います。
後はあまり印象ないなー。
名前の由来は、
作用機序に関連する、SGLT2(sodium glucose co-transporter 2)のローマ字部分 S・G・L・T をとって、スーグラ(Suglat)と命名したとのこと。
お、これはダイレクトなタイプですね!
いや別にすぐに楽にならないし。
この方向性で行くなら、私ならスグルト!を推したい。
ちょっと防御力上がりそう?
舌噛んだ?
昔はイオナズンとかのが好きだったのですが、
今はバイキルトとかスクルトの方が好きですね。
補助の重要性に気づいたのはメガテンや世界樹の影響でしょうか?
補助かけないと消し飛ぶからね。
かけすぎても消し飛ぶこともあるけど。
ルセフィ
次は大正のルセフィを見ていきましょう。
一般名はルセオグリフロジンです。
ルセフィって可愛くて好き!
そういう任天堂キャラいなかったっけ?
あれはスタフィーか、いやセルフィーか。
名前の由来ですが、
ルセフィ(Lusefi)は、一般名のLuseogliflozin(ルセオグリフロジン)+fineから命名したとのこと。
なお、ルセオグリフロジンの名称は、ラテン語で「光り輝く」を意味する「Luceo」に由来している。
何だよ普通だなーと思いきや、後書きで光り輝くに由来していると補足がありました。
光り輝く!
ラテン語使うと全部カッコよくなるのはなぜでしょうか?
あと輝く系、流行ってますね。
ルセオって何かのゲームで聞いた気がしたのですが思い出せませんでした。
何だろう?
一番近いのはオブリビオンのルフィオかな?
あのゲームは洋ゲーの楽しさを教えてくれたよいゲームでした。
勧めてくれた先輩も私も2児の母になってしまいましたね。
時の流れは早い。
アプルウェイ(デべルザ)
続きまして興和のアプルウェイです。
中外とサノフィも一緒に開発していますね。
むしろ中外の薬というべきか。
今はデべルザになっていますね。
一般名はトホグリフロジンといいます。
似ても似つかぬ一般名と商品名。
この由来を理解するためにはSGLT-2という系統の起源までさかのぼる必要があります。
1980年代になってリンゴやナシの樹皮に含まれる配糖体であるフロリジンが、SGLTを阻害することで尿糖排泄作用を示すことが明らかとなったのです。
これがSGLT-2阻害薬の起源になります。
この知見からSGLT-2阻害薬が開発されたのですね。
さて名前の由来はもうお分かりでしょう。
Apleway は Apple(りんご)と way(道、方法)の造語で、
リンゴの樹皮から抽出された物質を起源とした、
いままでの糖尿病治療薬にはない作用機序をもつ薬剤という意味があるのです。
リンゴの道なのですよ。
リンゴが示してくれた道というべきかな?
せっかくの道、ちょっと歩くの遅かったね。
カナグル
最後は田辺三菱のカナグルです。
一般名はカナグリフロジンと言います。
うーん、あまり印象深い薬ではないかな?
名前の由来は一般名の「Canagliflozin」と、
過剰な「Glucose(糖)」を尿中に排泄することで、健康な人と変わらない日常生活を過ごしたい糖尿病患者さんの希望を「かな(CANA)える」という想いを込めた「CANA」、及び「Glucose(糖)」の「GLU(グル)」から
カナグル(CANAGLU)と命名した。
え?一般名とグルコースだけじゃないんだ?
叶える!
あまり印象がないとか言ってごめんなさい。
患者さんの願いを叶える!という素晴らしい思いが込められていたのですね!
まとめ
さて、今日はSGLT-2阻害薬の名前の由来に迫ってみました。
単一のカテゴリーだったので、ついでに過去記事から系統の解説もおまけでつけてみました。
どれもなかなか濃ゆいお名前でしたね!
みなさんはどれがお好きですか?
私は由来から見るとアプルウェイですが、やっぱりジャディアンスかな?
泡立ち。
シリーズまとめ